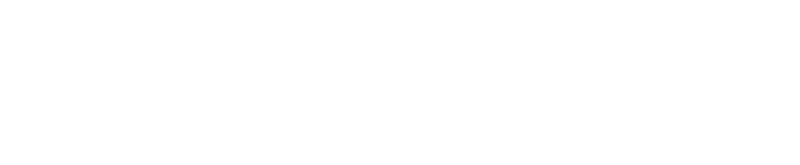銀座ポピュラスは平成世代を起点に、人と人が交わる空間をつくるプロジェクトです。
今回、その主催である僕たちふたりが、共通の知人であり人生の先輩である左右さんに聞き手をお願いし、なぜこの活動を始めたのかを語り合いました。
これまでの背景や銀座に「ホーム」をつくる意味をぜひ知っていただけたらと思います。
ふたりの出会い
澤井:上京して2、3年目ぐらいかな。まだ自分は何者でもなくて、田舎から出てきてキラキラした東京に圧倒されていました。日テレAXONの友人に誘われて「同世代が100人ぐらい集まる会が渋谷であるから澤井くんこない?」って誘われて行ったんですよ。芸能事務所、音楽レーベル、映画会社、出版社の同世代が大勢集まっていて。その会の主催者が菊地くんでした。
菊地:当時、制作のプロデューサーだったんです。映画や海外ドラマに関連した番組をつくる立場でした。地上波局に比べて人数が少ないので、地上波に比べると人が少なくて、ディレクターを経ずにいきなりプロデューサー。お金を動かし、事務所を口説き、制作会社に依頼させてもらうにも顔が利くかどうかがすべての世界でした。
同業の人と比べると時間の拘束は少ない。でも人脈がないと何もできない。だから人と会うしかないと思って、とにかくいろんな人に会いました。すると思わぬところから仕事につながる。マネージャー同士を紹介したら「ここ仮押さえが空いたのでどうですか?」と声かけが生まれたり、雑談から漫画雑誌の連載が始まったり。そうやって人の縁から仕事が生まれていくのが面白くて、飲み会もよく開いていましたね。そこで意気投合したのが澤井くんです。
澤井:その頃から思っていたのは、菊地くんは昔の出来事をよく知っている。普通こういう会の主催者って、ただにぎやかに飲みたい人が多い。でも会話の中で「上岡龍太郎が〜」なんて名前が出てきたりして(笑)。にぎやかに飲みたいだけじゃないんだなと思いました。そういえば渋谷で『約1分映画映画祭』をやったよね?
菊地:ただ飲むだけでは面白くないと思って。出版社や東宝、放送作家、電通のコピーライターなど、クリエイティブな同世代が短編作品をつくったらどうなるか? そう考えて上映会を開いたんです。澤井くんにも参加してもらって、らしさにあふれた作品をつくってくれました。
ルーツと価値観
菊地:僕は以前からテレビやお笑いタレントを「面白さ」と同時に「強さ」というモノサシで見ていました。ここでいう強さは単なる人気や芸歴ではなく、人間関係や文脈を背負い、その時代を象徴する存在であること。ルーツを辿って「こんな人がいたのか!」と発見するワクワクや、「この人から始まったんだ」と源流に触れたときの強者感やオーラ。どこか格闘技やプロレスを観るような感覚に近いのかな。
たとえばダウンタウンの先輩に紳助さん、さんまさん、関西にはやしきたかじんや上岡龍太郎。関東に目を向ければ、とんねるず、タモリ、ビートたけし、欽ちゃん。さらに60年代まで遡れば大橋巨泉さんやクレイジーキャッツ。時代と人がどう交差してテレビに登場したかを重ねて楽しむのが好きなんです。「80年代はこういう空気で、だからとんねるずが出てきた」みたいに。
大学時代はよくオフ会に参加しました。カラオケボックスで「吉本超合金」など昔のVHSをDVDに起こしてもらって、それを肴に語り合う鑑賞会。周りは30代〜40代のリアルタイム世代で僕だけ学生で。テレビって地域差や世代差があるので直撃世代の体験話を聴くだけで楽しかったし「80年代の空気ってどんなだったんですか?」と聞いて、その時代に思いを馳せるのが好きでした。
澤井:僕も似ています。基本的に「自分の知らない時代を教えてくれる人」が好きなんです。学生時代に出会ったのが、恩師の川村龍一先生。『ヤングおー!おー!』の司会をしていた方で、19歳の僕は毎日のように部屋に通っては当時のバラエティ史を教えてもらった。若手時代のさんまさんと一緒に遊んだ話とか、鶴瓶さんと一緒に麻雀した話とか、芸能界の話を隅から隅まで。先生の部屋に行ってずっとお喋りしていて、芸能界の空気を生で聴ける贅沢な時間でした。
川村先生は「大阪はお笑いのジャンルしかない。でも、東京に行ったら多種多様の才能がいる。20代の間に東京に行きなさい」と背中を押してくれました。実際、先生自身も若い頃に上京してゴールデン街で映画監督や政治家たちと飲み、同世代の仲間をつくっていたそうです。だから僕は吉本の養成所を卒業してすぐに東京に出てきました。

話は高校に遡ります。京都の東山高校に通っていて、周りは東大や京大に進むような進学校。僕は現役で失敗し、浪人した1年で人生が変わった。フジテレビの深夜番組『ふくらむスクラム』でオレンジサンセットの岡田さんを観て「同い年でこんなに面白い人がいるのか!」と衝撃を受けたんです。人生で初めて味わった嫉妬。そこから一気にお笑いにのめり込んでしまい、予備校より劇場に通う日々(笑)。現役で受かった大学にも落ちて浪人したくないから「吉本の養成所のNSCに行く」って言って母を泣かせているんですよ。
そのときに僕の父親が肯定してくれたんです。「大学で出会う友達とか環境で人生が変わる。大阪芸大なら学長は川村先生。直人が行きたい世界を誰よりも知っている人や」って大阪芸大のパンフレットを見せてきてくれたんです。父親が滋賀から伊丹まで車で連れて行ってくれて、川村先生と面接しました。すると先生は「こういう生徒が来るのを俺は待ってた。毎日僕の部屋に遊びに来なさい」と優しく言ってくださった。10代の頃に人生の指針を示してくれたのは、父と川村先生なんです。
今の妻とも大阪芸大で出会ってます。妻も川村先生のゼミで、仲間と一緒に白浜旅行にも行きました。川村先生は、僕が卒業した年に亡くなられた。奥さん(当時は彼女)に5月の誕生日を梅田のレストランで祝ってもらっていて。そのレストランの裏に先生の事務所があった。亡くなられたのは、ちょうどその時間だったの。不思議よね。
だから僕のルーツはそこなんです。年上と喋るのは楽しいですね。今の同性代の人たちって新しいものが好き。そこを全く否定するつもりはないのですが、やっぱり今キテるもの、これから来るものに目がいく。でも僕は逆です。時代は繰り返されているから、先人の人たちから学ぶ方がいい。でもその話ができる人が周りに全然いなくて。菊地くんはそれをわかってくれて、同じ目線で話せる人です。
銀座ポピュラス前夜と誕生
菊地:銀座ポピュラスの前にその前身になったものがあったんです。当時、25歳ぐらいの時に、1人1人にちゃんと話を聞きたくなった。芸能に関わるクリエイターに僕がインタビューして記事をまとめてそれでメディアをつくったんです。ウェブ制作もWordPressをゼロから勉強しました。
澤井:KUSAGIRIという名前で、銀座でイベントもやったよね。
菊地:そうそう。振り返るとチャレンジにはいつも澤井くんが関わってくれてたね。照れくさいけれど本当に心強い存在です。
澤井:僕も幹事として関わっていて同世代のタレントさん、事務所関係、出役から裏方まで、たくさんの同世代に声をかけて200人以上集まりました。今思えば銀座ポピュラスの原型だよね。そういう意味ではやりたいことは実はそんなに変わってない。
菊地:お互いライフスタイルも変わって、会わない時期が数年間あったんですけど。
澤井:コロナが明けてまた付き合いが戻ってきたんよね。久しぶりに会うようになって、菊地くんが改めて「人と人つないで新しいコラボレーションを生み出していきたい」と話してくれて。僕は伊集院静さんが歩いていた「銀座という街」を令和に残したいと伝えました。お互いのやりたいことを定期的にお茶をしながら、丁寧にすり合わせてきたんです。
菊地:「全く同じではないけど、この部分は共通しているよね」って。誰かから言われた仕事じゃないからこそ、お互いの主体性が噛み合うのが大事。そこは10年来の付き合いだから深く話せましたよね。
澤井:放送作家の大先輩の方たちとご飯に行くと、みんな口をそろえて「テレビ制作の場は、チームプレーだと。だから自分ひとりでやりきったものに出会えない」と言うんです。たとえ自分の企画から始まった番組でも、エンドロールの最初に流れるのは局員の名前で、作家は「構成」としか表記されない。
だからこそ自分で1本のエッセイを書ききったときの達成感は特別です。伊集院静さんについて綴ったエッセイや、週刊女性での「令和にんげん対談」。対談が決まった瞬間から相手のことばかり考え、当日を迎えて話を聞き、記事になる。そこで得られる快感は他には代えがたいものがあります。
「生きていくうえでホームをつくりたい」という想いがずっとあって、それが銀座ポピュラスなんだと思います。テレビや雑誌も素晴らしいけど、どうしても数字に左右されます。本当の気持ちに蓋をしてしまう、本当に会いたい人に会えない、本当に聞きたい話が聞けない。だから既存のメディアとは別の場所をつくりたかったんです。
僕がずっと伊集院静さんに会いたかったように、菊地くんも松岡正剛さんや上岡龍太郎さんに会いたかった。叶わなかった後悔をお互い語り合った時に「お互い一緒だよな」と共感し合いました。同じ平成世代はもちろん、下の世代にも同じ思いをしてほしくない。だからこの場(銀座ポピュラス)を使ってほしい。

菊地:もう一つ観点があるとすると、コロナを経て気づいた「固定化」の問題です。30代を過ぎると、自分の半径何メートルで仕事も生活も回るようになる。会社に所属する人はもちろん独立した人も「このチームに入っておけば生活もできる」のようなケースって周りを見てると案外ある。うまくいっている人ほど意外と落ち着いてしまう。でも、それって新たなチャレンジの余白を削ってしまう罠だと思ったんです。
だからこそ僕らが機会をつくって、同世代が新しい人と出会えるようにしたい。平成世代の面白い人たちから深く話を聞く。その人が会いたい人と実際に会えるように橋渡しをする。そうやって小さな化学反応を起こしていきたいですね。
銀座ポピュラスは、究極の「まかない飯」だと思っています。締め切りもないし、やらなければ何も生まれない。でも自分たちが本気でやりたいからこそ続けられる。もちろん、やるからには多くの人に届けたいけど、筋肉の使い方が違うから新鮮なんですよね。
澤井:この前は二人で話したのは、まず僕ら平成世代の同世代と、そこまで知り合いが多くないよね?って。同じテレビ業界には知り合いがたくさんいます。でもあえて業界が異なる同世代にもどんどん会いたいねっていう話をしてて。ひとりの人からじっくり話を聴くこともやりたいかな。
菊地:いま『新百姓』という雑誌づくりにプロジェクト参加して感じるのは、さまざまな職種かつ東京以外の地方で、クリエイティビティに溢れる仕事をしている人がめちゃくちゃいます。僕ら自身が交友を広げつつ、その関係を可視化していく。そこから次の対談や、新しい企画が生まれていく。そういう連鎖を生み出したいですね。
澤井:「この二人となら一緒にやってみたい!」と思ってもらえる関係を築いていくのが大事。好きになってもらう努力も必要だし、最初から完璧を目指す必要もない。これから育てていけばいい。そうやって同世代の素敵な人たちと知り合って、死ぬまで関係が続いていったら最高じゃないですか。
愛川欽也さんや長門裕之さんが中心になって結成された昭和九年会のイメージとも近いかな。藤村俊二さんのワインバー『O’hyoi’s』で毎月会が開かれていたんですよね。僕らも、そういう場を令和に持ちたいんです。
これからのこと
澤井:笑われるかもしれないんですが、僕の夢は「死ぬまでに日本人全員と話すこと」なんです。いわば「人間ライブラリー」をつくりたい。まさにそれが銀座ポピュラスだと思っています。
菊地:僕はクリエイティビティを発揮する、いろんな人たちの創発の起点になれれば最高ですね。今回お話してふと思ったのは、芸能に携わる人たちが書いた本を集めたライブラリーをつくっても面白そう。文脈の置き方次第では、まったく知らない人でも楽しめる気がしていて。そういうアクセスできる空間をおすそ分けできる場所がリアルであってもいい。
たとえば銀座ポピュラスというBARにいくと面白い人や本に出会えるイメージです。人から辿っていくとテレビ黎明期の人物や落語、そして文学作家にも行き着きます。当時って全然ジャンルが違う人でも交わっていて、いまもウェブ記事やpodcastはありつつも、昔は対談本が多かったですよね。
澤井:昔は昭和の小説家たちが対談本を出すのが主流でした。向田邦子さんの『お茶をどうぞ』、開高健さんの『午後の愉しみ』、吉行淳之介さんの『やわらかい話』とかね。
菊地:そうだね。当時は出版社が取り持っていて、本にならなくても密室で行われていた。ネットがないからこそ、クローズドならではの人間関係。たとえば赤塚不二夫さんの赤塚会や、山下洋輔さんがタモリさんを福岡から呼び出したスナック「ジャックと豆の木」。彼らの拠点は新宿ではあるものの銀座的。では今はどうかというと、映画監督の山田洋次さんが川村元気さんとの対談本『仕事。』で「そういう場が減った」と嘆いていました。
澤井:今、銀座に若い世代が集まって語る夜がないんですよ。あの昭和の匂いがなくなっている。池波正太郎さんも「東京から匂いがなくなっていっている」と危惧されていました。人の勉強させてもらった場所は銀座って伊集院さんも言われてますね。昭和の水商売には人情がありました。伊集院静さんが売れる前に通われていた店の『銀座グレ』の光安久美子ママが伊集院さんや若手業界人に優しく、値段を安く飲ませてくれたそう。全部、いい話は銀座が舞台だったじゃないですか。そういうふうにしていきたい。
人を惹きつける銀座
澤井:銀座は「ナカ」と「ソト」で言えば「ナカ」。伊集院静さんをナカに連れ出したのはデザイナーの長友啓典さんでした。「伊集院、ほなボチボチナカ行こか」と。そこで大人の世界を学び、人の勉強をした。奢られることは、その人の価値を映すことでもあるんです。
僕自身も少しずつ奢る立場になって、「この人と飲みたい」と思える相手は限られてきた。伊集院さんは「奢りたい」と思わせる人でした。20代の頃は逗子なぎさホテルに11年間、家賃を払わずに住まわせてもらった逸話もありますよね。
菊地:だからこそ、そういう「人を惹きつける力」を持つ人たちが自然と集まる場を再現したい。伊集院さんが体験した銀座のポテンシャルを、僕らの世代なりに再定義したいんです。みんなの頭の中にあるイメージを活かしながら、銀座ポピュラスを同業に限った内輪空間で閉ざさずに「集まれば化学反応が起きる場」として育てていきたい。
澤井:余談ですが、僕が敬愛する伊集院静さんのエッセイを書くきっかけは菊地くんが起点なんです。リアルサウンドの編集長を紹介してくれて『伊集院静さんが好きすぎて』という連載を始められた。それを伊集院静さんの娘の西山繭子さんが読んで、伊集院静さんご本人にも伝えてくださっていた。伊集院静さんが亡くなられたあとに繭子さんが手紙で送ってくださったんです。人と人とをつなぐ連鎖の先に生まれた出来事で、本当に感動したし、僕の人生の宝物です。
さいごに
菊地:これからお会いする方からすると、僕らは違うジャンルだからこそハブになれると思います。そのためには自分自身が日々を面白く生きていないと説得力がない。銀座ポピュラスは、僕ら自身の背筋を伸ばしてくれる存在でもあるんです。
「時間の流れ」って不思議ですよね。5歳にとっての1年は人生の20%だけど、60歳にとっての1年は1%台。歳を重ねるほど時間はどんどん短く感じる。だからこそ、一つひとつの時間を大切にしないと、あっという間に過ぎ去ってしまうと思います。
澤井:人間、あっという間に死ぬって言いますね。
菊地:時間の早さと濃さって別物だよね。本当に楽しい経験って早く過ぎたか遅いかさえも忘れるんじゃない?
澤井:死ぬ前に走馬灯のようにフラッシュバックする瞬間ってあるじゃないですか。きっと、早く感じた濃密な時間こそ候補に残るんだと思う。今日はそういう日ってことだね。
――「悠々として急げ」
「ゆっくりと急げ」という意味のこの言葉は、ローマ帝国初代皇帝アウグストゥスの座右の銘であり、開高健も好んだ言葉です。焦らず着実に、けれど必要なときには一気に進む。銀座ポピュラスもまた、この言葉のように育っていけたらと思います。

澤井直人 放送作家
1990年(平成2年)生まれ。
『大悟の芸人領収書(日本テレビ)』『人生で1番長かった日(日本テレビ)』などを企画。他、『一茂×かまいたちのゲンバ(日本テレビ)』『ザ・ノンフィクション(フジテレビ)』『タイムレスマン(フジテレビ)』などを担当。小説家・伊集院静を敬愛し『伊集院静さんが好きすぎて。』を執筆。東京と京都の二拠点生活。ものづくりのテーマは“ザ・人間”
菊地将弘 プロデューサー|事業開発者
1991年(平成3年)生まれ。
放送局で配信ビジネス領域で活動。個人活動では、書籍のマーケティング支援『「知る」を最大化する本の使い方』、K-PROライブ「サツマカワRPGがテレビで売れるための企画たち』プロデュース、インタビューメディア「KUSAGIRI」主宰など。趣味は本屋巡りと空手。「つくり手たちの世界が交わる場所を増やす」ことが最近のテーマ。