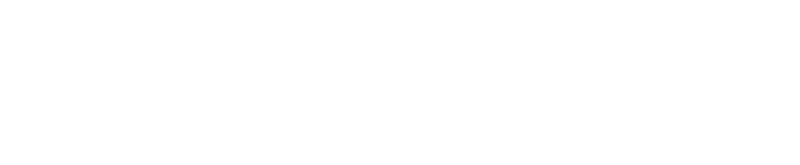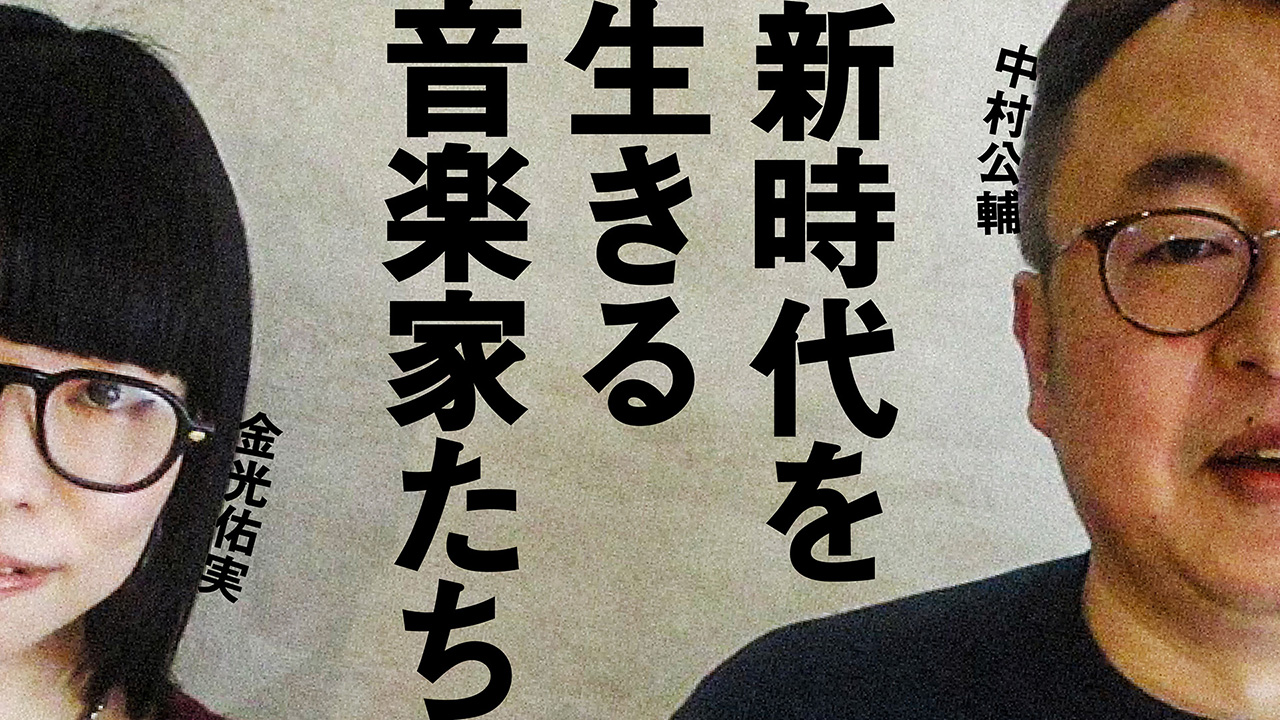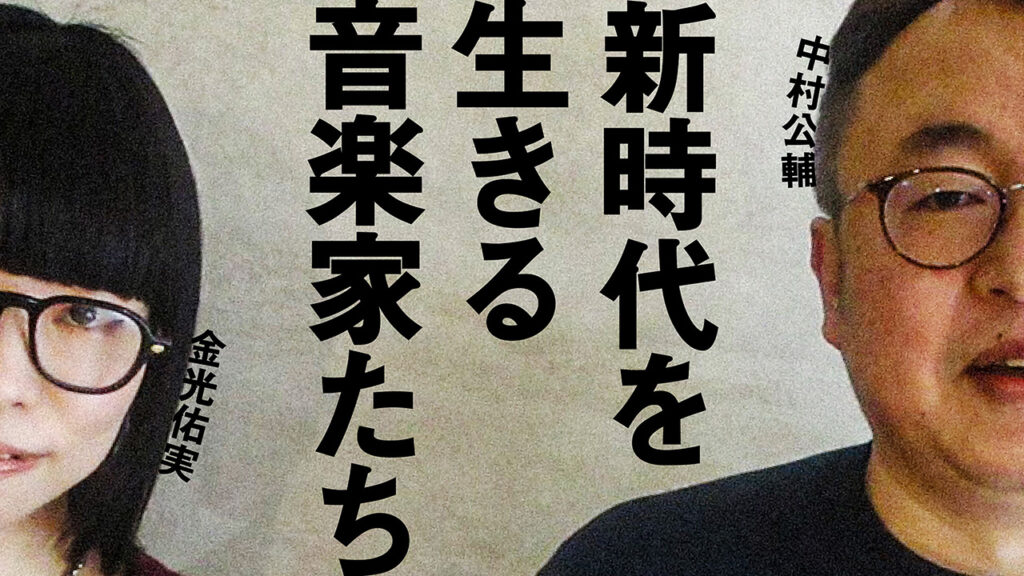

中村:だからこの先の5年ぐらい、20代でバンドやる人って、よっぽど裕福な人かものすごく尖ってるかに限られてくる。
金光:わかります。コロナ前ですら、人と予定を合わせてスタジオを取って、曲を定期的につくるのって重労働だったし。ブランク期間があったら、さらにハードルが上がりますよね。
中村:そう。ライブハウスだって、誰かに教わらないと「どうやってライブするの?」ってなっちゃう。電話? メール? いくらかかるの?って。
金光:たしかに(笑)
中村:でも、コロナ禍にも面白い変化は起きていて。
金光:ほお〜。

中村:今までだったら、オルタナっぽいバンドだと、ギターがガーッとひずんでいたら、そのひずみに合わせてシャウトしなきゃいけないわけじゃないすか。
全部がホットな音楽になる。でもコロナ渦で洋楽の変化として、同じ場所でライブで演奏するんじゃなくてリモートで制作してるだけだと、他の楽器に負けないようにする必要もない。
金光:はい、はい。
中村:だから、すごい轟音のギターを鳴らしてても、ボーカルはすごくソフトだったりする。なんていうか耳に刺さらない轟音というか。家の中でも心地よく聴ける轟音が出てきてる。この5年くらいで、そんな面白い変化があったんですよね。コロナが明けたら、またちょっと「はっちゃけた」音も戻ってきてるし、これからも変わっていく気がします。
金光:はっちゃけた音ってどんなかんじですか?
中村:ソフトじゃない音がちょいちょい出てきてるね。これはもうちょっと前からだけど、AOTYを見てると、チャートにメタルが混ざってきてるとかね。人が外に出始めると、音楽もまた変わるんですよ。
金光:うわ、面白い。
ジミヘンより3倍長く生きられるなら
中村:同世代の友達と話すんですけど、けっこう前のめりでいかないと本当にアウト。みんな会社勤めしてたら60歳定年じゃないですか。もう疲れたから今自分ができることをやったまま「今のうちに逃げ切れたらいいな」みたいな雰囲気になっちゃう。
金光:なるほど。
中村:そうなってくるとね、フレッシュに面白くてやってる感じじゃないから。 話すことも「一刻も早く仕事を辞めたいんだよね」って内容ばかりになって、つらくなってくる。
金光:消化試合みたいな。
中村:よくないんですよ。ちょっとドキッとする話だけど、昔に比べて寿命って今、倍ぐらいじゃないですか。
金光:はい。はい。
中村:明治とかだと、平均寿命が40代とかですからね。
金光:えっ、当時でもまだそんなもんだったんですね!
中村:そう。昔の人はすごい大人に見えるけどさ、夏目漱石だって49歳で亡くなってるし。そこからみるみる寿命が延びていって。だから僕は「年齢を半分でカウントする」って考えるようにしてる。
金光:それは名案ですね!
中村:なので僕は今ちょうど今年50になったので25!これで生きていくみたいなね。25かって思うか、それとも残りもオマケを生きてるって思うか、どっちか。
金光:それもめっちゃいいですね!
中村:実際、オマケだしね。最近の遺伝子研究だと「この動物は何歳ぐらいが本来の寿命か」がわかるようになってるらしくて。それで人間を調べたらどうやら37歳ぐらいらしい。

金光:えええ!
中村:普通に生きてたらそんなもんらしいんですよ。
金光:じゃあ、私はもうすぐ死にますね(笑)
中村:だからね、そこから先はもう死んでると思えばいい。適当でいいんですよ。
金光:オマケって考えるのと、まだ25歳って考えるのと、どっちもいいけど結局の行き着くところは同じ気がしますね。
中村:うん。だって、わからないですからね、120歳まで生きるかもしれない。昔の寿命感覚だと、「この年齢でこれぐらいやってないと!」って基準があったじゃないですか。
金光:ありましたね。
中村:何かここから先、面白いことがあるとしたら、たとえば「20代を終えて40歳くらいまでの20年で、ひとつ成果を出して終わる」それが以前のモデルだったと思うんですけど。今はその20年を、あと2〜3ターン繰り返せるんですよね。そうすると、昔はひとつの分野しか極められなかったけど、2つも3つもプロになれるじゃないですか。
金光:はい、はい。
中村:昔の偉人ってすごいじゃないですか。ベートーヴェンになれないとか、ジミヘンにはなれないとかって、つい思っちゃうんだけど。
でもジミヘンより3倍長く生きられるなら、違う形で何かに到達できるかもしれない。合わせ技でたどり着ける場所ってあるんじゃないかって、最近考えていますね。
金光:それは音楽の中でってことなんですか?それとも全然別の可能性も?
中村:それはわからないね。今のところは他のこと考えないようにしてる、ちょっと調べすぎちゃうから(笑) 何でもやったら面白いですからね。
金光:いや、そうですよね。たしかにどんなことでも突き詰めていったら、めちゃくちゃ面白いですよね。
中村:そう。いくらでもできますよ。
金光:なんか、心が軽くなる話ですね。
クラシックの巨匠たちも必死だった
中村:この前、いろいろベートーヴェン関連の資料を見てて。
金光:えっ、何でですか?
中村:いや、いろんなこと調べているんですよ。ベートーヴェンって、交響曲や名作を何本も書いて音楽だけで食ってきたすごい人生みたいに語られるじゃないですか。調べてみたら全然そんなことない!
金光:へ~!
中村:元々は超絶技巧の天才ピアニストとして登場していて。めちゃくちゃに早弾きができるピアニストで、かっこいい曲を書くタイプ。イングヴェイ・マルムスティーン(メタルの速弾きができる人)みたいに20代前半で世に出て。
金光:へえ。
中村:貴族からの支援も受けてね。自分の作品だけで食ってきたように見えてるけど、当初はそんなことはなくて。
「この街にとどまってくれるんだったら、これぐらい払うから引っ越せないでくれ」みたいに言われて、当時の金額で年収2000万ぐらいのお金を貴族からたぶんもらってたんです。だから好きなことを割とやってられんな!てかんじ。
でも、そこでハイパーインフレが来るんですね。それでめっちゃ金もらってたのに、固定給でもらってたお金がすべて無価値になっちゃって、それでド貧乏になっていて。
そこに耳が聞こえなくなる。もう絶望して、弟に「死にます」みたいな遺書を残して。そこからですよ、交響曲を書き始めるのは。
金光:え、そうなんだ。
中村:あの9つの交響曲は、耳が聞こえなくなってから書いたもの。そう考えると、すごいなと。
金光:基本的に私たちは曲しか知らないですもんね、ベートーヴェンって。
中村:しかもそこから先、死んだときにはかなりの財産があったらしい。それはなぜかというとインフレのリスクがあるから。ちゃんと生活できるようにしなきゃいけないと、収入の大半を株に突っ込んでいたんですね。
ほとんどの資産をオーストリア銀行の株で持ってて、亡くなったときには国の上位5%ぐらいの富裕層だったそう。意外となりふり構ってないんですよ。
金光:なりふり構ってないですね。
中村:めちゃくちゃな人が、意外とちゃんと残ってるんですよ。たとえばハイドンもそう。貴族の支援を受けていた世代なんだけど、水上の音楽とか──ああいうちょっとバブリーな曲を書いてるでしょ。
金光:はい、はい。
中村:実際、生活もバブリーで、最初は貴族の子弟に教えていたんだけど、そこから自分で劇場をつくって、「イベントを大量に打つ!」ってことを始めて。
普通だったら採算取れないんだけど、そこに来てた金持ちの子弟たちに年間パスポートみたいな仕組みを導入して、
「劇場にいつでも好きなときに来てOK」にした。今で言うサブスクですね。それを株式会社化して、どんどんデカくしていって、ああいう派手なイベントを次々にぶちあげていた。
金光:めっちゃ商売人ですね。へえ、すごい。音楽室に写真が飾ってある芸術家ってイメージだったけど、じつはバリバリの実業家だったんですね。
中村:そうなんですよね。逆に同世代のバッハは、教会付きの作曲家として雇われて、ちゃんと給料もらって仕事していて。
今だったらゲームメーカーの社員として作曲しているようなノリかもしれない。当時からそれなりに尊敬をされているけど、近所でライブやるって聞いたバッハが「ちょっとハイドンに会いに行きたい」と手紙を書いても無視されていたらしい。
金光:へ~!
中村:ビジネスパーソンとはちょっと違うんですよ。 そういう教会でずっと書いている作家だから。バッハは一応、教会の庇護(ひご)のもとにいるからお金もあるし子供にも継がせたりしてるけど、音楽的には全然評価されてなくて。
実際、評価されるようになったのは、死後200年ぐらい経ってからです。スコアが残ってたから評価されたけど案外わからないもんですね。
未来は、また誰かがつくりなおす
中村:昔はね、いろんな時点で何かそういうテクノ(技術)でまた評価される場合もあるし、繰り返しになるけど、やっぱりスコアが残ってたからこそ評価されたって部分は大きいよね。
金光:そういう現物が残ってるのは大事ですよね。今はネットに放流できるけど、データが膨大すぎて、そこから発掘されるのは相当むずかしい。
中村:そうね。
金光:TikTokとか、ああいうとこから謎に発掘されることありますよね。
中村:ほんとに、何が残るかなんてわからない。
金光:いや本当ですね!何が起こるかわかんない。
中村:結局、あとから出てくる人次第だしね。この話、ずっと続けられちゃうんだけど(笑)。クラシックだとその後、古典派、印象派が出てくるじゃないですか。
印象派は日本ではよく聞かれてるけど、瞬間的にしかたぶん食えてないんですよ。 ドビュッシーだとかサティが出てきた後に印象派を勉強して、ああいう曲をつくっている人はべつに食えてないじゃないですか。劇伴(=劇中音楽)作家になるしかない。そういう人たちがそのまま死に絶えていったかっていうと、音楽を教えるぐらいしかないとかね。
でもね、そういう作曲家の弟子がアメリカに渡って生徒をとって、その中からジャズの大御所が生まれた、みたいな話もあるんです。だから、また復活することだってある。
金光:何が起こるかわかんないんですよね、本当に。
中村:たとえば、ドビュッシーとビル・エヴァンスを比べて聴いてみると、ブルースが入ってないビル・エヴァンスって、まさにドビュッシーみたいじゃない?
金光:たしかに。本当にそうですね。そう言われてみると。
中村:案外どこもつながってるから。何かを引っ張ってきて何かとつなぐっていうだけで新しいことってできたりする。
金光:たしかにもうゼロから新しいものをつくるって、むずかしいですよね。
中村:何かシステムごと最初からつくっちゃうとか、そういうことをやれば新しいものができるけど。
金光:なんなら楽譜の概念を変えるみたいな。
中村:そう。実際、今までも何度もつくり変えるってやってきてるわけだから。あとはこの枠の中でつくるのも、最初からつくる側で決めちゃってるからできないって思ってたけど、その時代の考え方や哲学に共鳴する形で、新しいものって生まれてきたと思うんですよ。常にそうだったと思う。
金光:そういう運動って、またこれからも起きると思いますか?たとえば騒音芸術みたいに、ノイズが芸術になるような流れとか
中村:……つくろう。
金光:いいですね~!!!
正解はひとつじゃない音楽の歴史
中村:最近は合理的に何かをやるフェーズじゃないですか。タイパとか言ってさ。
金光:ほんとそうですね、タイパ、コスパ。
中村:そうなってるじゃないですか。合理的にやることのパフォーマンスの悪さってのをみんな無視してるよね。瓜二つのものを大量生産する工程なんかは合理化できると思うんだけど、発見とか創造みたいな、唯一無二のものを一度だけやればいいものに合理化って不可能だと思う。そういう世相とか思想を反映させた音楽を作るんだったら面白みを感じるけどね。
金光:でも後から振り返ったときに、実はここはこういう社会情勢だったからこういうかんじが生まれただとか、後から評価されるようになるんですかね?
中村:どうだろうな。聴く側は、単体で絵や音楽に触れるだけで、そこまでは考えないかもしれない。
でも、つくってる側はたぶん「違う枠」を提示しようとしてると思う。最初はめちゃくちゃに聞こえているものでも、一回受け入れられちゃえばそれがすごいいいものになっちゃうから。たとえば中世の音楽。あの頃って最初グレゴリオ聖歌は、旋律は1本しかありえなくて。
金光:はい、はい。
中村:なぜかというと、キリスト教が一神教だから。
金光:へえ!
中村:だからだから「正解は1つ」しかありえない!メロは1本。それを全員で同じメロを歌うっていう。
金光:はい。
中村:でも実際は初期からハモりはあって。理由は単純で教育を受けてないだとか、年齢が違いすぎるだとか、そういう理由で同じ旋律を歌えないから。子供と大人が一緒に賛美歌を歌ったらさ、高い低い差が出てきちゃうじゃん。それでハモるしかない。しかもハモると気持ちいいじゃないすか。
金光:そうですよね。
中村:たぶんね、ハモると気持ちいいっていうのを出しちゃうと、教会の権威が揺らぐんですよ。
だって教会という場所自体がオーディオのようなものだから。でかい権威がある教会に行くとめちゃくちゃ響いて、もう単旋律で歌ってても、うわーって気持ちいいじゃないですか。
ド田舎に行って歌っていても何にも気持ちよくないわけですよ。それよりハモった方が圧倒的に気持ちいい。でも、当時はハモるのは邪道だったんですよね。
金光:はい、はいはい。
中村:絶対にハモらない世界があったんだけど。
金光:笑っちゃうような話だけど本気だったんですよね。
中村:そこにルターの宗教改革がぶっこまれてきて。それで急に「三和音が三位一体を表してる」とか言い出して。
金光:こじつけにもほどがあるんですけど!
中村:そうそう。だけど、そういう流れでハモってOKの匂いになってきた。
金光:みんなやりたくてしょうがなかったんでしょ!
中村:それで、ちっちゃい教会でもハモった方が気持ちいいってなってくると、でっかい教会の権威性が揺らぐ。宗教改革って、そういう側面もあるんだと思う。歴史の変わり目って、たぶんそういうのがちょいちょい起きてる。
金光:なるほど。宗教改革がそういう始まりだったと。
中村:だから、あれだね。うちらのちょっと前ぐらいの世代までは思想を勉強する人がけっこう多かったけど、ここ最近は基本的にマネーの話に寄ってるよね。景気が悪いからかな。
金光:そうですよね。社会全体がそうなってますよね。
新自由主義って、誰のための自由?
中村:でもね、それって甘やかしでもあるんですよ。新自由主義って、言った方が得する人がいるってだけの話で。こんな話してて大丈夫?(笑)
スタッフ:もちろんです!
金光:新自由主義って?
中村:元々70年代ぐらいにアイン・ランドが小説に書いた思想なんですよ。縁故主義だとかに囚われず社会を変えていくために無駄を排していくみたいな考え方なんだけど。ちょっと意味合いが変わってきちゃったからね。 「保守を守るために削ぎ落としていく」みたいな、何か保守側の論理で語られるようになっちゃって。
金光:全く逆の話になったってことですね。
中村:謎ですね。日本ではそういう結びつきになっちゃってるかなと。だからそういうのを「やっちゃえ」って体現したのがジョブズのような人たち。本来的にはいろんな圧力がかかっても世の中が良くなって新しいことができるんだったら「やってしまえ」みたいな。そういう思想だったのにちょっとね、違う話になっちゃって。
金光:そうですね。印象がだいぶ違いますね。
中村:だからタイパとかも、「やりたいことをやるために何を切るか」って話ならわかるけど「やりたいことを切って、お金のために動く」ってなっちゃうとね。
金光:おかしなことになってきますよね、本末転倒っていう。
中村:怪しい話になってきました。